講座の主旨
2015年に都市農業振興基本法が施行され、都市農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと転換しました。これを受けて都市政策においても2017年の都市緑地法の改正により、農地も緑地として都市政策に組み込まれ、都市農地の保全が進められるとともに、都市での「農ある暮らし」のニーズがますます高まっています。
そこで日野市でも、農業振興と緑地を含めた都市農地保全の取り組みや、農業経営の実情、市民の農への参画、地産地消の推進、持続可能で循環型の社会づくり、歴史などを学ぶ連続10回の講座を2024年11月から開催しています。
(主催:農あるまちづくり講座 in 日野市実行委員会、共催:都市農業研究会、一般社団法人TUKURU、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 東京三多摩山梨事業本部、協力:日本社会連帯機構、農的社会デザイン研究所、日野市、後援:JA東京みなみ)
第8回講座
今回の講座では、ワーカーズコープ三多摩山梨事業本部の扶蘓文重さんが「労働者協同組合」とそこでの働き方の特徴である「協同労働」について解説くださった後に、山梨市のブドウ園などの実践事例をいくつかご紹介くださいました。
講座の内容や様子は、JA東京みなみが初回分からホームページにアップ下さっています。こちらからご覧下さい。

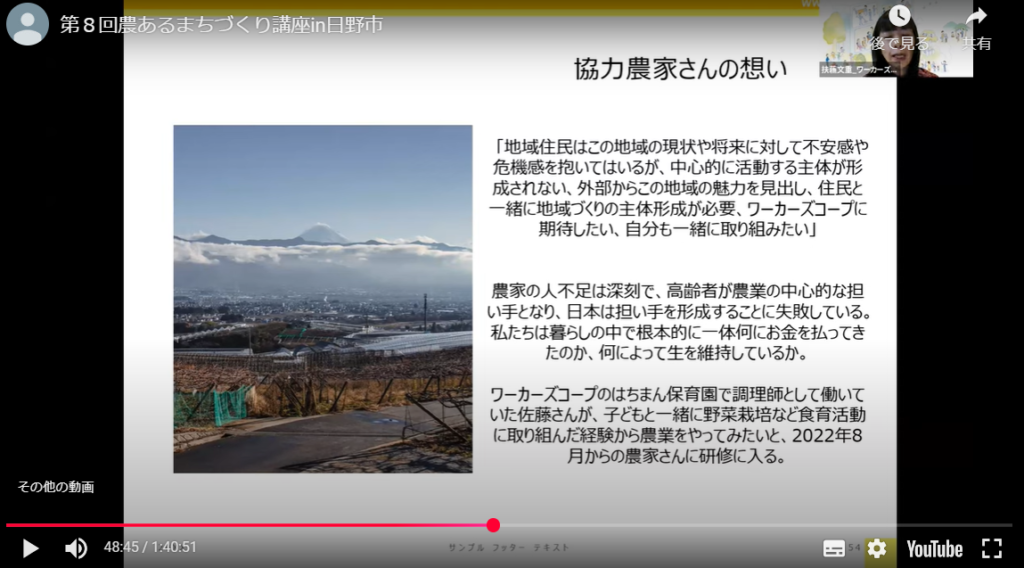
私が印象に残ったこと
みんなで出資して、対等な立場で話し合って、みんなで働くという協同労働。「職場をコミュニティに変える」という取組みは、とても魅力的に感じました。職場=コミュニティで働く人たちだからこそ、地域にコミュニティを広げていけるのでしょう。
私が遊ばせてもらっているコミュニティ農園も、職場ではないけれど、協同労働的なコミュニティです。それぞれが会費を出して、「今度はこれをつくってみたい!」と何をどこに作付けするのかもみんなで決めて、みんなで学びながらはたらく。作物ごとの担当はあるにしても、その日参加した人たちで協力しながら作業をする。ダイコン、ネギ、キャベツなどなど、作物が人間を結びつける。作物の数だけ結び目があるネットワークという感じで、とても心地よいのです。
そして今回のお話を伺って、以前読んだ本にあった言葉を思い出しました。それは心身障がい者や薬物依存者、元受刑者などを受け入れているイタリアのワイン農場で働いている人の感想です。
「有機農業は自分に合っていると思う。人と話さなくてもいいしね。それに農業というのは、人間が植物を育てるのかと思っていたけど、そうじゃなく、ブドウの樹自身や土の中の微生物が働いているんだよ。それまで僕は、人間とブドウの樹しか見えていなかった。他には誰もいないと思っていたんだ。でも本当はそこには、いろんな草やいろんな微生物の大群衆がいるんだよ。一人でやる孤独な仕事じゃないんだ。」(松嶋健さん『プシコ ナウティカ ~イタリアの精神医療の人類学~』2014年 世界思想社)
畑って、人間を超えて多様な生きものまで広がる協同労働の場なのですね。
(小牧)